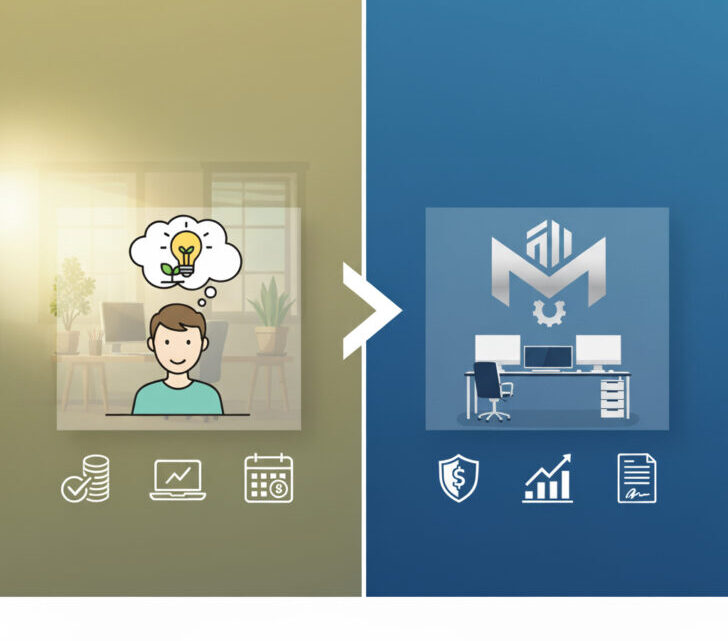
個人事業主とマイクロ法人の違いを徹底解説!【メリット・デメリット比較】
これから事業を始めようと考えている方や、現在の事業形態を見直したい方にとって、「個人事業主」と「マイクロ法人」のどちらを選ぶべきかは大きな悩みどころです。
この記事では、両者の違いを分かりやすく比較し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
一目でわかる!個人事業主とマイクロ法人の比較表
まずは、全体像を掴むために主要な違いを表にまとめました。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 法人格 | なし | あり |
| 設立手続き | 開業届を提出するだけで簡単・無料 | 定款認証や登記が必要で、費用と手間がかかる(合同会社で約6万円~) |
| 社会的信用度 | 法人に比べると低い傾向 | 高い(融資や取引で有利になることも) |
| 税金 | 所得税(累進課税)、住民税、個人事業税 | 法人税(一定税率)、法人住民税、法人事業税 |
| 収入の扱い | 売上 – 経費 = 所得 | 法人の売上から役員報酬として給与を受け取る(給与所得控除が適用) |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金(全額自己負担) | 健康保険・厚生年金(会社と個人で折半負担) |
| 経費の範囲 | 事業に関連する費用 | 役員報酬、退職金、社宅家賃など、より広い範囲を経費にできる |
| 赤字の繰越 | 3年間 | 10年間 |
| 赤字の場合の税金 | 所得がなければ所得税・住民税はかからない | 赤字でも法人住民税の均等割(最低年7万円程度)は発生 |
| 事務負担 | 比較的少ない(確定申告) | 複雑(決算申告、社会保険手続きなど) |
それぞれのメリット・デメリット
比較表だけでは分からない、具体的なメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。
個人事業主
メリット
- 始めやすい:開業届を税務署に提出するだけで、費用もかからず手軽に事業を始められます。
- 事務作業が楽:法人に比べて経理や税務申告がシンプルです。
- 赤字の場合の負担が少ない:所得がなければ所得税や住民税はかかりません。
デメリット
- 税金が高くなる可能性:所得が増えるほど税率が上がる「累進課税」のため、利益が大きくなると税負担が重くなります。
- 社会保険料の負担:国民健康保険料は所得に応じて上限なく増えるため、高額になることがあります。
- 社会的信用度が低い傾向:法人に比べて、金融機関からの融資や大企業との取引で不利になる場合があります。
- 経費の範囲が狭い:自分への給与や退職金は経費にできません。
マイクロ法人
メリット
- 税金・社会保険料を最適化できる:役員報酬を調整することで「給与所得控除」を利用でき、所得税を抑えられます。また、社会保険料も役員報酬額に基づいて決まるため、国民健康保険料より安くなる可能性があります。
- 社会的信用度が高い:法人格があるため、金融機関からの融資を受けやすくなったり、取引先からの信頼を得やすくなったりします。
- 経費にできる範囲が広い:自分への給与(役員報酬)や退職金、社宅の家賃の一部などを経費として計上できます。
- 赤字の繰越期間が長い:赤字を10年間繰り越せるため、将来の黒字と相殺して節税できます。
デメリット
- 設立・維持にコストがかかる:設立時に登記費用(合同会社で6万円~)がかかります。また、税理士への依頼費用なども発生します。
- 赤字でも税金が発生する:事業が赤字でも、法人住民税の均等割(年間最低7万円程度)を支払う義務があります。
- 事務手続きが複雑:年に一度の決算申告や、社会保険の手続きなど、個人事業主より事務負担が増えます。
まとめ:自分に合った事業形態を選ぼう
個人事業主とマイクロ法人には、それぞれ一長一短があります。
- 手軽に始めたい、売上がまだ不安定 → 個人事業主
- 売上が安定し、節税や社会保険料の最適化をしたい → マイクロ法人
また、最近では「個人事業主+マイクロ法人」の二刀流で、両方のメリットを活かすスタイルも注目されています。
この記事を参考に、ご自身の事業規模や将来の展望に合った最適な形態を選んでください。